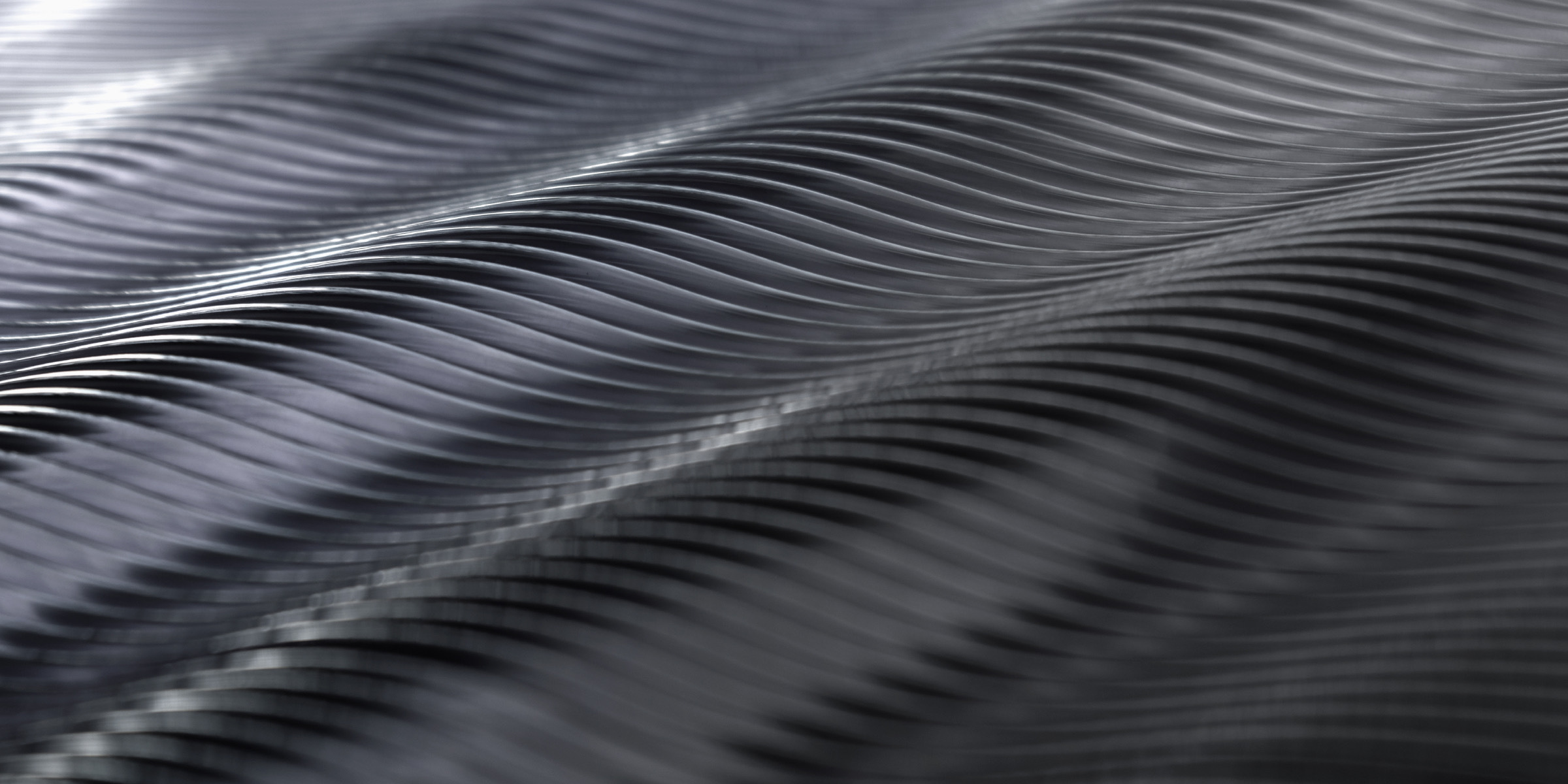INTERVIEWS
SPECIAL INTERVIEW | .Gab×IIISU
炭で描く、廃棄物ゼロの未来。
独自の炭化技術を使い、プラスチックや衣服、食料残渣など従来は焼却されていた有機系廃棄物を炭の粉末へと変換。人工皮革をはじめとする多様な“選べる素材(再資源)”へと生まれ変わらせる新循環ソリューション「.Garbon(ガーボン)」が誕生した。この画期的な技術を社会実装する仕組みをつくったのが、創業から6年のスタートアップ・株式会社Gabの山内 萌斗氏だ。環境問題の本質的な解決に挑む過程で越えるべき壁を見出した山内氏は、廃棄物を使用したスタイリッシュなパイプイスを作品として発表しているIIISU(イイイス)と運命的な出会いを果たす。今年のデザイナート東京では、共鳴し合う両者が初めてコラボレーションした作品が展示される。作品の魅力をたどることで浮かび上がった、「.Garbon(ガーボン)」が描くあたらしい世界とは。
「意識高いね」という壁。
山内 萌斗/株式会社Gab 代表取締役CEO 株式会社Gabは、「Garbage breakthrough=ゴミ問題の打開策」を主なテーマに社会課題の解決に取り組むスタートアップです。これまで展開している事業はゴミ拾いとゲームを組み合わせたエンタメイベント「清走中」や、人・動物・地球にやさしい商品を集めた国内最大級のECプラットフォーム「エシカルな暮らし」など。「清走中」は全国でイベントを開催していますし、「エシカルな暮らし」は有楽町マルイでの実店舗を運営し、売上も伸び続けていました。ある程度の手応えは感じつつも、いわゆる “キャズムを超えた”実感が得られていなかった部分があり…。僕が最も難しさを感じていたのが、そもそも事業テーマが「意識高い」と思われがちであること。起業家同志で話せば盛り上がるけど、地元の友達に話すと「意識高いね、頑張ってるね。」って少し敬遠されてしまう。このギャップを埋めるにはどうしたらいいのか模索する中で、IIISU(イイイス)さんに出会いました。僕が感じている難しさをものづくりで突破しているクリエイターがいると聞いて、とても興味を持ったんです。
熊谷 嵐/IIISU 僕らは「見落としているものを心に刻む活動をしよう」ということを理念に、いま5名のメンバーで「IIISU(イイイス)」というブランドを展開しています。よくみなさんが使われるパイプイスの背もたれや座る部分を皮や布、木材などさまざまな廃材に貼り替え、作品として発表してきました。最初の1脚は僕の思いつきでつくったものだったのですが、多くの方に求められるようになっていき、現在はPOPUPやアトリエで販売も行っています。
山内
インスタを見て驚きました。作品が、見たこともないようなかっこいいものだったからです。僕らと同様に廃棄物をテーマにしながら、すごいイケてる人たちに刺さっていた。僕が超えられなかった境目のようなものをかっこよさで超えていると感じました。ひとめぼれのような感じで、すぐにお話ししたいと打診しました。それが2年くらい前のことですね。
熊谷
僕らも、かっこいい作品が作れている自負はありました。しかし、逆にビジネス的にこの先どう広げていけば良いのかと悩んでいる時期でもありました。萌斗君が作品を見にアトリエに来てくれたときにこちら側からも相談を投げかけたら、ちょうどいい壁打ちができたというか、廃棄物をテーマに世の中に価値を生み出そうという思いが通じ合っていて楽しかった。なにか一緒にできたらいいねとそこからよく会うようになりました。萌斗君と話していると、悩んでいた部分が晴れていくようなイメージが持てたんです。
山内
出会った当初はまだ「.Garbon(ガーボン)」の構想は僕のなかになくて、既存事業のご相談などをしていました。でも事業におけるパッションが共通するIIISUさんと議論するなかで少しずつかたちになっていきました。僕はもっと直感的に人々が惹きつけられるようなサービスやプロダクトをつくって、会社をもう一段上の段階に押し上げたかった。4年にわたり展開している「エシカルな暮らし」では300社以上のブランドを取り扱っていましたが、自社でプロダクトを持っていなかったんですよね。これまでの販売データやユーザーインサイトを基盤に自分たちのブランド、オリジナルIPを持ちたいなという考えもあった。IIISUさんは自分たちで企画から制作、販売まで一気通貫でやられていました。つまり自分たちでブランド運営されていたから、そこも学ばせてもらいたくて。そんなときに教えてもらったひとつの事例にインスピレーションを得たんです。
熊谷
あれは、液状化させた紙を直接日本酒の瓶に塗り、パッケージとした「塗紙」という事例でしたね。それ以外にも、デニム工場で廃棄される部分を塗料に使った左官材「塗るデニム」などの事例も面白いなと思い話しました。新しいものをつくることは、結局最終的にゴミになったり廃棄される運命にあります。それならばそもそも捨てられてしまうものをアップサイクルすることで新たになにかを生み出すのが良いのではないかと。素材のような何かに化けやすいもの…特に内装材などは面積も取れるし、市場を獲得しやすいんじゃないかな、と思って。
山内
モノをつくるという方向ではなくて新たな素材をつくったら加工の仕方もさまざまでインパクトが大きいかもしれない。その発想から.Garbonは生まれています。あの日本酒のパッケージは本当に素敵だったな。
かっこいい、がまず最初に来なければ。
山内
最高の素材をつくって、それをあるブランドが採用してくれたら、そのファンは「好きだから、かっこいいから」という理由で買うでしょう。社会ためになるから買うのでは、やっぱり意識高い人のためのものになってしまう。好きで買ってみたら社会を良くするものを使っていたという現象を目指したかったんです。あと、これは余談になりますが、ブランドをつくることについて熊谷さんたちと話していたときに自分を見つめ直した点がありまして…。
熊谷
なんですか?
山内
お話しを伺っていて、常にものづくりのことを考え、人生をかけて没入して、実際に手を動かして作品をつくらなければ本当にかっこいいものはつくれないと分かったんです。やすやすと「ブランドをつくりたい」なんて言っちゃダメだな、本気度が違ったなって、1回ちゃんと考えなおしたんですよ。
熊谷
そんなことがあったんだ(笑)。ブランドづくりについては、かなり語りましたね。少しIIISUのことをお話ししますと、僕は普段、サインディスプレイの会社で働いています。あるとき僕が事務所でパイプイスに座りデスクでPC作業していたんですけど、パイプイスってお尻が痛くなるじゃないですか。これ、スポンジを張り替えたらいいんじゃないかなと思って。ちょうどそのとき僕が欲しいなと思っていた革張りでダイヤ型に張り込んだ20万円くらいのソファがあったのですが、そんな感じのものつくれないかな、と思い、YouTubeを見ながら技術を習得して、廃材を集めて作ってみたんです。そうしたらオフィスに来るデザイナーやアーティストさんたちから「かっこいい!」「それ、売ってよ。」というリアクションがあった。これ何か可能性があるのかな、自分のブランドをつくってみようかなという思いが湧いて、同僚に声をかけたんです。
IIISUの作品は廃材を使ったものだけど、いくら環境によくても、やっぱりかっこよくなかったら人は手に取らないですよね。それこそ意識高い人は結構買ってくれるかもしれないけど、それ以上広くは行きわたらない。だから僕たちが大事にしているのはかっこいいもの、欲しいと思えるものをまずつくることなんです。先ほど話に出たデニムの左官材も、最初の感想は「環境にいいね」じゃなくて「これかっこいいね」でしたから。
山内
IIISUさんたちのようなアート性というか、センスを持つ方々ってそんなにいないですから、僕たちが会社として再現性を持って事業を拡大していくためにはそういうクリエイターさんたちに渡せるモノをつくることがいいなと話していて思ったんです。人を熱狂させるものづくりが実は社会課題解決につながっているとなれば、社会的なインパクトが最大化するんじゃないかなって。
熊谷
アートで、かつ使い道がある、というのも大切にしていますね。たとえば座面にトゲトゲがあって座れないけどコンセプチュアルで素敵だな、という方向ではないということです。使うから伝わるものがあるだろうって思っているんです。また、コラボするならば志が同じ人と、というのもポイントですね。いま僕らは、会社では人のつくりたいものをかたちにしていますが、IIISUでは自分たちがつくりたいものを第一にしよう、というのも大事にしていることだから。
.Garbon(ガーボン)の新規性。
山内
IIISUさんから色々学ばせていただいて、.Garbon(ガーボン)を企画し始めたのが1年前くらいのことです。「エシカルな暮らし」を運営するなかで、さまざまな企業から「うちの技術、なにか事業にならないかな」とご相談を受けることが増えていました。そのなかのひとつに.Garbon開発を支えてくれたパートナーである大木工藝さんがありました。有機化合物を炭化する技術で多くの実績を持っていらっしゃって、プラスチックやペットボトルはもちろん、服も、食品残渣もタイヤもビニール傘も…あらゆるものを炭にした実績をお持ちでした。炭は、多くの高機能な工業製品に使われていることを知っていたから、これはもしかしてゴミがなくなる日が来るんじゃないのか?というくらいの衝撃を受けました。いま、廃棄物を原料として再利用するマテリアルリサイクル率は20%と言われています。まだ80%はサーマルリサイクルとして燃やされているんです。でも、この技術を使えば確実に30%に、もしかしたら50%に引き上げることも遠い夢じゃないと。大木工藝さんは滋賀県にある創業55年の企業で、早速僕は社長に会いに行きました。80歳である社長は半端じゃなく知識を持った方で、技術チームも常識を超えた発想と情熱を持っていました。唯一の課題が、ビジネスをつくることだったんです。場所柄採用が難しかったり、PRやブランディングなど世の中に打ち出していくことを苦手とされていた。あと、僕が感動したその技術は彼らにとって当たり前すぎて、テンションが低いんですよ(笑)。これめっちゃすごいことですよ!って、僕の方が熱くなって語りました。
山内
いま、いろんな企業が脱炭素と資源循環でCO2を減らすソリューションを探しています。リサイクル率100%を目指したいという声もいままでたくさん聞いてきました。廃棄物は燃やすと二酸化炭素などのガスがうまれ、最後には灰になります。一方で、炭化技術は無酸素下で加熱するためCO2を減らすことができるうえ、廃棄物中にある炭素を「炭」として固定化することができるんです。僕は、この技術はさまざまな事業の可能性につながっていることを社長に話しました。じゃあ、君、なんか勢いがあるからやってみてよと言っていただき、独占ライセンス契約を締結しました。
.Garbonの最もユニークな点は、入口と出口のレパートリーの多様性なんです。あらゆる廃棄物をまとめて炭(C)にした、それを分解することでどんな素材にも配合できるようにしているのがポイントなんです。炭化した炭をさらに細かいパウダーに加工し、その一粒を顕微鏡でみると穴がたくさんあいています。それが匂いやウイルス、水分を吸着するんです。
熊谷
炭は消臭抗菌効果があると言いますが、そういうことなんですね。
山内
そうなんです。.Garbonで最初に開発を着手した素材は人工皮革だったのですが、炭を革の中に入れたら機能を付加した素材ができるという仮説を立てました。既存事業で展開したアップルレザーはりんごジュースの搾りかすを入れた人工皮革製品でしたが、そのストーリー性がヒットにつながった。ヒントはそこから得ました。実際に炭のパウダーを入れた人工皮革は消臭抗菌効果がSEK認証を取れるレベルに上がったことがわかりました。さらにパウダーをもう一段細かくすると、インクにも使えるんですね。つまり顔料にできる。僕はいつか、世の中の黒いものをすべて廃棄物由来にしたいと思ってるんです。
熊谷
なるほど。最近の萌斗君の口癖が「それ、炭にしませんか?」なのも納得できます(笑)。
山内
インクに使えるレベルまで細かくすると穴がなくなるから機能性は落ちるんですけどね。ただ黒はかなり幅広く使われている色だから、可能性は広がると思うんです。炭化したものをどこまで分解するかによって情緒性・機能性・汎用性と強調する部分が変わる。それが出口の多様性と言っている部分です。.Garbonなら、誰かにはハマるようなプランができるのではないかと思っています。
変容の意思
熊谷
今回、萌斗君とコラボレーションして作品をつくるにあたり、デザイナート東京2025のコンセプトにあった「機能美と本能美」について深掘りしてみたんです。.Garbonにあてはめて考えてみると、機能美を追求してさまざまなものを均質化し、そこから塗料にしたり左官材にしたりレザーにしたりと、個性を際立たせて本能に訴えかけるプロダクトへ広げていく、ということになります。これ、すごく面白いなと思って。そしてこのプロセスは「学校の授業」に近いのではないか?と。学校って、子供たちを同じ教室に入れて、同じイスに座らせて教育することで「均質化する」と言えますよね。でもそれは個性を抑圧しているのではなくて、個性を生み出すベースをつくっているんじゃないかなと思いました。「均質」と「個性」は対立しながらも、互いを支え合う関係にあると考えたときに、学校と.Garbonに重なるものを感じたんです。
山内
たしかに.Garbonに通じるところがありますね。均質化された素材だからこそ、新たな個性と魅力がある、さまざまなものに変化することができます。
熊谷
そうなんです。それで学校の象徴ってなんだろうって思ったときに「机とイス」にたどり着いた。役割を終えた学校の机とイスと.Garbonの素材を組み合わせて生まれ変わらせたらどんな個性のある作品になるだろうと。今回展示される作品は完成形でもなくて、イスはそのまま座ってもいいし、机は什器として使ってもいいし、使う人によって変わる可能性を示すものでありたいと思って。それが変容の意思という作品タイトルにつながっています。
山内
熊谷さんの話で再解釈できました。
熊谷
まず前提として、機能美があるからこその本能美なんですよね。それを勇敢に示していける環境を僕らはつくっていきたい。みんなが見落としているものをかっこいいって思える世界をつくっていきたいというのがもともとIIISUの考え方でもあるから、.Garbonとデザイナートと我々の思いがシンクロするところに生まれたのが今回の作品であると思っています。
山内
機能美がない時代は、本能美を追求する余裕はなかったですよね。そう考えると「これかっこよくない?」を表現できる、幸せな時代を僕らは生きています。先人たちの恩恵を受けながら、もっと人間の幸せを追求していきたいとも思う。今回の作品は.Garbonの可能性をIIISUさんに最大化してもらった事例のひとつです。展示をご覧になる方に、「廃棄物」というイメージからかけ離れた新しい世界があることを伝えられると嬉しいですね。こんなこともできるのかと驚いて欲しい。
熊谷
そうですね、機能美マジありがとうと思っています(笑)。今回僕らは、コンセプトの設計と作品づくり、そして展示のアートワークまで担いましたが、今お話ししたような思いを素材や作品で示したいと思っています。
山内
IIISUさんたちが現実でしっかり “売れている”、つまりファンがたくさんいるのって、無難なものづくりではないからなんですよね。「エシカルな暮らし」を運営するなかで、売れるのはやっぱり差別化できるプロダクトだとよく分かりました。IIISUさんはそこを本当にいいバランスでやっていらっしゃるなと思います。
熊谷
僕らは今、照明をつかった作品にもトライしているところです。自分たちがつくる「いい」を誇れる世界というのを目指す、僕たちの今後の活動もぜひ楽しみにしてほしいです。また、素材はあるけどこれはどうかっこよくなるだろう?みたいなご相談があれば、気軽に声をかけていただけると嬉しいです。
山内
僕らは、リサイクルや資源循環を諦めていた企業が.Garbonと出会い、炭化という選択肢によって希望を持てるようになることを目指しています。ブランド名.Garbonの前にドットがあるのは、「終わりの始まり」という意味を込めているんですよ。廃棄物が価値ある商品に生まれ変わる。つまりゴミ削減と、コスト削減の両立を実現できるのがこのソリューションです。廃棄物に課題を抱える皆さんに、ぜひ展示を通して僕たちの取り組みを知っていただければと思います。
Interview and Text : Sayoko Shimizu
BRAND / CREATOR
![]()
![]()
山内 萌斗
株式会社Gab 代表取締役CEO
2000年浜松市生まれ。
静岡大学情報学部在学中に、社会課題を「。ユニークに解く」株式会社Gabを起業。ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」、国内最大級のエシカルメディア&ストア「エシカルな暮らし」、あらゆる廃棄物を"炭化"し素材に変える「.Garbon」などを展開。
https://www.gab.tokyo
![]()
熊谷 嵐
IIISU
2021年からIIISUを発足。「見落としていたモノをこころに刻む」をコンセプトに作品の制作を行っている。
大道具とサインディスプレイに技術のルーツを持ち、様々なバックボーンを持つIIISUメンバーとともにアートワークを展開。
IIISU インスタグラム
https://www.instagram.com/iiisu_2021/
.Garbon (ガーボン)サービスサイト
https://garbon.tech/